

旅館業(簡易宿泊所)の
申請の流れ
民泊やゲストハウスの運営を行うには各自治体の指定の窓口へ必要な書類を提出し、許認可を受ける必要があります。
許可なく営業することは違法になります。
それでは、申請から許可取得までの大きな流れを解説してみます。
ご注意ください
ここでは1日1組が貸し切りで利用できる民泊やゲストハウス(簡易宿泊所)の申請を行うことを前提として開設を行います。
※法律や条例は変更されることもあり、またすべての条件に当てはまる内容ではない旨、予めご了承ください。
1事前調査
所有している物件、或いは、購入を検討している物件が民泊やゲストハウスに適しているのか確認します。
-

用途地域
都市計画に基づいて土地の利用方法が定められています。住宅専用地域や工業地域では簡易宿泊所の営業は難しいと考えておくとよいでしょう。
-

建物の所有権(権利)
簡易宿泊所の申請は家族所有の物件や賃貸物件でも可能です。しかし、いづれの方法にしても申請をして営業することについて所有者の承諾書が必要です。
-

建物の構造
3階建ての建物は消防法の制限もあり、3階が利用できない。また、建築基準法制定以降の建物では、厳しいバリアフリーの協議があり、建物の利用が大幅に制限される可能性があります。
-
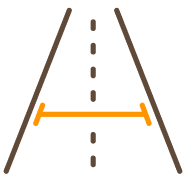
通路幅
都市計画に基づいて土地の利用方法が定められています。住宅専用地域や工業地域では簡易宿泊所の営業は難しいと考えておくとよいでしょう。
-
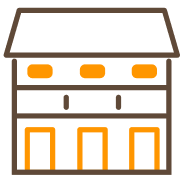
連棟の建物
京都でよく見られる長屋(連棟で構築された建物)。これは1つの建物として認識される為、延べ面積が500㎡を超える場合防火区画を設ける必要があります。
-

建物の登記状況
特に町家など古い建物の中には、増築部の未登記があることが非常に多いです。行政側も未登記部分を利用面積として認めるわけにはいかない為、再登記や部分的な解体が必要なケースがあります。
2各種行政機関との事前協議
建物の状況や今後の計画について、自身の理解や意向がそのまま受け入れられるとは限りません。
あくまでも判断をして許可をするのは役所の窓口です。大きな資金が動く内容ですので、事前相談は必須です。
旅館業の申請

保険福祉局
医療衛生センター
旅館業の申請を行う窓口です。
少なくとも平面図や登記資料、地図上での配置や建物写真など建物の詳細がわかる資料と自身の計画についてプランを持参します。

担当:行政書士等
基本的に行政への申請業務などは、行政書士等が担当し、旅館業の窓口との折衝や書類の作成、近隣との調和業務等を行います。
消防設備に関する工事

所轄の消防署
建物の構造が詳しくわかる資料が必要です。
平面図に加えて、窓の位置、収納の扉の有無や広さ図面に詳細を記載するのが難しい場合は、各部屋の状態が確認できるように各部屋四方の状態を撮影しておきます。

担当:消防設備士在籍の設備会社
消防設備に関する工事については、消防設備士の資格を持った設備会社に工事を依頼して、申請書類も作成します。
施設の構造や設備

建築審査課
登記情報との相違がないか、建物の構造上、宿泊業を行うことに問題がないか確認します。またバリアフリー法の「合理的配慮の提供」義務化に基づく施設の構造や設備について

担当:建築士
図面の作成や登記情報との紐づけ、行政の建築部門との折衝などを建築士が担当します。そのまま建物の設計まで担当するケースもあります。
どの分野も専門的な内容であり、経験のない方がすべてそれぞれの専門家と計画の調整をし、書類を作成していくのはとても困難なことです。打ち合わせの回数も重なり進行状況を把握するだけでも手一杯になるでしょう。
オーナー様に代わり、それぞれの専門家と申請が円滑に進むように調整を行います。

3建物の工事計画
必ず必要となる工事は消防設備工事です。普段から建物のコンディションに気を使って利用しているケースでは、
リフォーム工事を行わなくても、そのまま宿泊施設として利用できることもあります。
しかし、収容人数を増やす、単価アップの為、間取りを変更したり水回りを充実させるオーナー様は多いです。
-
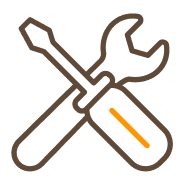
消防設備工事
宿泊客が火災や停電といった緊急時に安全に避難できるように誘導灯や非常照明などの設備を設置し、避難経路図や消火器も備えます。
-
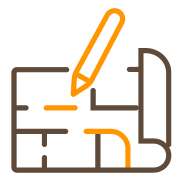
旅館業の要件確認
申請上、重要な設備はトイレ、浴室、換気設備等です。5名以上宿泊させたい場合トイレや洗面を増設する、室人数を増やすなど間取りを改装するといった工事を行います。
-

バリアフリー対応
玄関のスロープ、通路幅の確保、段差の解消、手摺や昇降機の設置、床の誘導ブロックなど、建物の構造によって求められる要件は異なります。
4各種申請手続きの開始
建物の状況を把握しその場所で旅館業ができることが確認できどのような宿泊施設にするのか、
プランニングの準備ができたら、申請のプロセスが開始となります。
-

学校等への意見照会
施設の敷地内から四方110m以内に学校などの教育施設や福祉施設がある場合、
適正な運営を確保に関する手続きを行います。風紀の維持や児童の健全育成を図る為です。【標識の設置】
営業許可申請をしようとする日の20日前から設置 -

計画の公開
近隣にお住いの方や町内会長へ計画の内容について説明を行います。
旅館業施設建築等指導要綱に基づき、施設の前に計画概要を示した標識も設置します。行政の計画承認まで20日間
-

バリアフリー協議
玄関のスロープ、通路幅の確保、段差の解消、手摺や昇降機の設置、床の誘導ブロックなど、建物の構造によって求められる要件は異なります。

5各種工事の着手
ステップ3で計画していた工事を施工します。ステップ4のフェーズで待機期間がある為、その期間中に工事内容に関する詳細な打ち合わせや材料の発注などを行い、申請に要する期間の短縮を図ります。
消防設備に関する工事や申請、現地調査が完了すると1週間から2週間後に「消防適合通知」、そしてバリアフリー法に関連する工事が完了し協議が終了すると検査済証が発行されます。

6旅館業の
営業許可申請
計画していた工事がすべて完了したら営業許可申請を行います。
各種機関から受け取った検査済なども一緒に提出します。
書類に不備等がなければ、最後のステップへ移ります。

7京都市の職員による現地検査
保険福祉局・医療衛生センターの担当者が実際に施設を訪問し、申請書内容に相違がないか、建物内で各部屋の採寸や設置備品の確認などを行います。
この時、ベッドや布団については、申請した定員の数を用意しておく必要があります。その他、多言語で解説されたハウスルールやキッチンの操作方法の確認も行われます。検査後、問題がなければ凡そ1ヶ月から1か月半程で許可証が発行されます。
実際の旅館業申請の
イメージは掴めましたか?
こちらのページでもご紹介した通り、簡易宿所等の許可申請は、個人で完遂するには想像以上にハードルが高い作業です。
実際、私たち自身も自社物件の申請を数多く手がけ、そのたびに一から全てのプロセスを自力で対応してきました。だからこそ「不可能ではない」が「決して簡単ではない」ことを実感しています。
当ページの内容は、全体像をつかんでいただくことを目的としており、実際の現場ではさらに細かな手続きや準備が数多く必要となります。
また、物件の構造や立地条件によっては、必要書類が増えたり、調査・準備にかかるコストや時間が大きく変わる場合もあります。
もし、対象の物件が弊社で管理可能な条件であれば、これまで数百件以上の許可申請をサポートしてきた私たちの経験と専門知識を最大限に活かし、
申請から取得までを一貫して全力でサポートいたします。

京都の民泊運用は
お気軽にご相談下さい
-
Webからのお問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
受付|10:00~20:00
閉じる
-
Webからのお問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
受付|10:00~20:00









