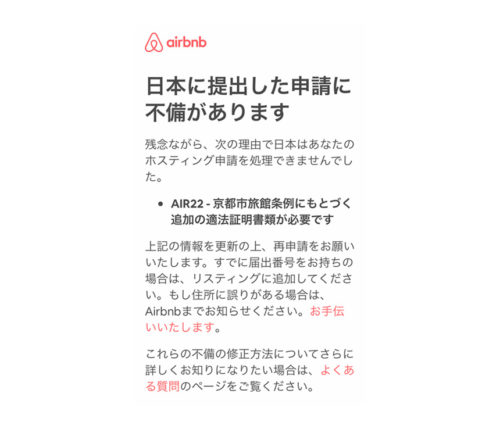民泊情報ブログ
京都市、観測史上初の「60-60」到達~異常な猛暑が観光と経済にもたらす変革
2025年9月15日、京都市は今年の猛暑日と熱帯夜の日数がそれぞれ60日に到達し、日本国内で観測史上初めて暑さの「60-60」という記録を達成しました。これは、1年の約6分の1が猛暑日と熱帯夜に当たるという「異常な猛暑」を意味し、昨年、全国で初めて記録した「50-50」に続き、2年連続で前例のない猛暑となっています。この記録的な暑さの背景には、高気圧の強い勢力と地球温暖化が複合的に影響しているとみられています。
京都市が盆地であることも猛暑の一因です。本来、盆地は日中、風が弱く強い日射で気温が上昇しやすい一方で、夜間は放射冷却で気温が下がりやすい特徴があります。しかし、近年は都市化が進んだことで、夜間も気温が高いまま維持される傾向にあります。今夏は、チベット高気圧と太平洋高気圧の勢力が特に強く、史上最も早い6月27日頃に梅雨明けしたことで好天が続き、猛暑日が頻発しました。これに長期的な地球温暖化が加わり、今回の記録的な猛暑につながったと考えられています。
9月中旬にもかかわらず、京都市内は朝からよく晴れて気温が上昇し、真夏のような暑さに見舞われました。嵐山の渡月橋では、日傘や扇子を手に、暑そうに歩く観光客の姿が目立ちました。同日午後2時現在、猛暑日が60日に達したのは京都市と大分県日田市(60-21)の2観測点のみであり、他の主要都市の記録は、国内史上最高気温を記録した群馬県伊勢崎市が49-42、大阪市が44-77、名古屋市が51-70、東京都が29-52となっています。このデータからも、京都市の猛暑がいかに特異な状況であるかが伺えます。
目次
猛暑が京都の観光・経済に与える影響
この記録的な猛暑は、京都の経済、特に観光業に深刻な影響を与え始めています。
観光客の減少と行動の変化
猛暑により、観光地では「異変」が相次いでいます。京都市内の観光スポットである東映太秦映画村では、ミストなどの暑さ対策を講じているにもかかわらず、7月と8月の来場者数が前年比で2割から3割減少しました。観光客からは、「着物でのお稽古も着物なんですけど今日はやめました。ギブアップしました」といった声や、「もう嫌。できれば秋っぽい感じになってほしい」といった切実な声も聞かれます。
また、観光客は暑さを避けるため、涼しい時間帯や場所への移動、涼を感じるアクティビティへの関心を高めています。これは世界的にも見られる傾向で、記録的な熱波により観光名所が閉鎖されたり、旅行者がより涼しい「クールケーション(coolcation)」と呼ばれる目的地へ移動したりする動きが強まっています。欧州では北部沿岸地域で観光需要が拡大する一方、南部の一部地域では夏の観光客が約10%減少する見込みです。日本でも、激しい蒸し暑さに見舞われる地域が多い中で、札幌などが「クールケーション」先として人気を集めています。
夏の風物詩への影響と新たな定番化

京都の夏の風物詩である「納涼床」にも猛暑の影響が及んでいます。割烹「露瑚」では、熱中症や食中毒の対策として、7月の平日と8月の全ての日でランチ営業を中止せざるを得ませんでした。ようやく9月1日から再開したものの、女将は「まだまだ暑そうやなっていうのがちょっと不安ですね」と語っています。例年は9月末までの営業ですが、今年は暑さの影響で10月中旬まで延長されており、納涼床が夏の風物詩ではなく、「秋の定番」となる可能性も指摘されています。
間接的な経済影響
猛暑の影響は、意外なところにも表れています。ホームセンター「コーナン」では、6月から8月までの蚊の殺虫剤などの売上が、昨年と比べて1割減少しました。害虫防除技術研究所の実験によると、蚊は25度から30度で活発になる一方、35度以上になると活動量が減り血を吸わなくなるとされています。現在は蚊の活動が鈍いものの、気温が下がると活動が活発になる可能性があるため、10月下旬までは対策が必要だと注意を促しています。
猛暑を乗り切る「涼」の提供と新たな観光スタイル
「とにかく暑い!!」というイメージが強い夏の京都ですが、京都市内ではこの猛暑に対応するため、様々な工夫を凝らした「涼」のスポットや体験、イベントが提供され、新たな観光スタイルが模索されています。
涼しいエリアへの移動
京都市街地より気温が5度から10度ほど低くなると言われるのが、鴨川の上流に位置する「貴船(きぶね)」エリアです。古くは「氣生根(きぶね)」と記され、「氣が生まれる根源の地」を語源とするこの地は、古くから「涼」の地として知られています。夏の貴船では、貴船川の真上に設けられた「川床(かわどこ)」で、せせらぎをBGMに食事を楽しむことができます。五感で涼を感じられ、時には肌寒く感じることもあるため、薄手の羽織があると良いでしょう。水の神様を祀る貴船神社では、「水占みくじ」や「御神水ラムネ」も楽しめます。
「朝観光」の推進
気温が上がる前の涼しい時間帯に観光を楽しむ「朝観光」が推奨されています。嵐山・嵯峨野の竹林の小径は京都を代表する観光地ですが、日中人であふれる竹林の小径も、午前8時頃までなら比較的混雑なく、涼しく楽しめる魅力があります。サラサラと竹の葉ずれの音色も心地よく、心身共に浄化されるような体験ができます。
世界遺産東寺では、一般拝観開始前の早朝に、僧侶の案内で特別拝観ができるプランが日にち限定で開催されています。暑くなる前の時間帯に少人数で拝観できる上、金堂や講堂だけでなく、通常非公開の五重塔初層や小子房なども巡ることができます。参加の記念に限定御朱印も授与される特別感あふれる内容です。
また、世界遺産二条城では、通常非公開の「香雲亭(こううんてい)」で、庭園を眺めながら季節の食材を使った朝食を楽しめる企画が実施されています。毎年趣向を凝らしたメニューが提供され、優雅な朝の時間を過ごすことができます。
「影」を活用した涼と夜間の体験
厳しい日差しを避け、お堂の中や境内の木陰から寺院の庭園を鑑賞する「影の涼」も提案されています。影によって作られる涼空間で、じっくりと庭園の風情を味わうことができます。
北野天満宮では、8月の御手洗祭から10月の瑞饋祭にかけて「御手洗川足つけ燈明神事」が再興されています。祈願したい御利益に応じて五色のろうそくを選び、境内の御手洗川に足を浸して心身を清め、ろうそくに火を灯し献灯する神事です。日中も体験できますが、川面にろうそくの灯りが揺れる日が落ちた夜が特におすすめとされています。
世界の都市に学ぶ猛暑対策
京都市の猛暑は特異な状況ですが、世界各地の都市も記録的な熱波に苦慮しており、観光客が暑さをしのげるよう様々な対策を進めています。これらの事例は、京都が持続可能な観光と都市づくりを進める上で参考となるでしょう。

アブダビでは日中の気温が51.8度に達することもありますが、古来の手法と最先端技術を組み合わせた猛暑対策に取り組んでいます。世界有数の持続可能な都市であるマスダールシティでは、太陽光パネルでエネルギーを賄うほか、伝統的な風の塔「バルジール」を現代風にアレンジし、狭く日陰のある街路や建物の配置で気温を下げる工夫をしています。
中国北部の大都市ハルビンは、避暑地として台頭しています。冬の有名な氷祭りを夏にも取り入れ、広大な屋内施設に氷像を設置したり、先進的な造雪技術で屋外でも雪を降らせたりしています。
日本では札幌が「クールケーション」先として人気を集めています。札幌は独自の暑さ対策として豊富な雪を活用し、冬の間にためた雪を溶かしてその冷水を空調に利用するシステムをモエレ沼公園や商業施設で導入しています。
パリでは7月の熱波でエッフェル塔を閉鎖するなど観光客に影響が出ましたが、公園や森、プール、美術館などに「クールアイランド」800カ所強を整備し、休息できる場所を提供しています。近隣の涼しい場所を案内するアプリ「Extrema」もダウンロードでき、2030年までに約6万台分の駐車スペースを樹木に置き換える計画もあります。
米国で屈指の暑さを誇るアリゾナ州フェニックスは、都市の冷却対策で世界をリードしています。同市の「涼しい舗装」計画では、太陽光を反射する明るい色の特殊素材を道路に塗布し、路面温度を最大で約8.9度下げる効果があります。
まとめ
京都市の「60-60」到達は、地球温暖化と都市化が複合的に引き起こした異常な気象現象であり、京都の観光と経済に多大な影響を与えています。しかし、京都市は盆地特有の暑さに対応するため、貴船のような涼しい避暑地の活用、早朝観光の推進、夜間の体験、五感に訴える「涼」の提供など、様々な工夫と新たな観光スタイルを模索しています。
同時に、世界各地の都市が直面する猛暑とその対策事例は、京都にとって貴重な学びの機会を提供しています。持続可能な都市開発、環境に配慮した観光プロモーション、そして市民や観光客が安全かつ快適に過ごせるようなインフラ整備は、今後ますます重要となるでしょう。京都市の「60-60」という記録は、単なる気象記録に留まらず、都市のあり方と観光の未来を問い直す契機となっています。
京都の民泊運用は
お気軽にご相談下さい
-
Webからのお問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
受付|10:00~20:00
閉じる
-
Webからのお問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
受付|10:00~20:00